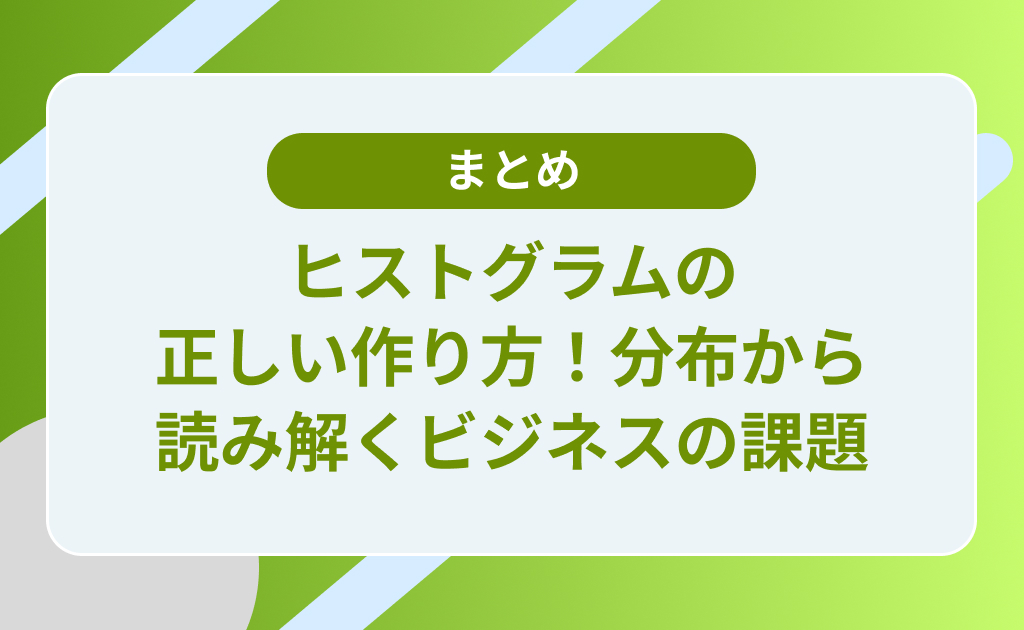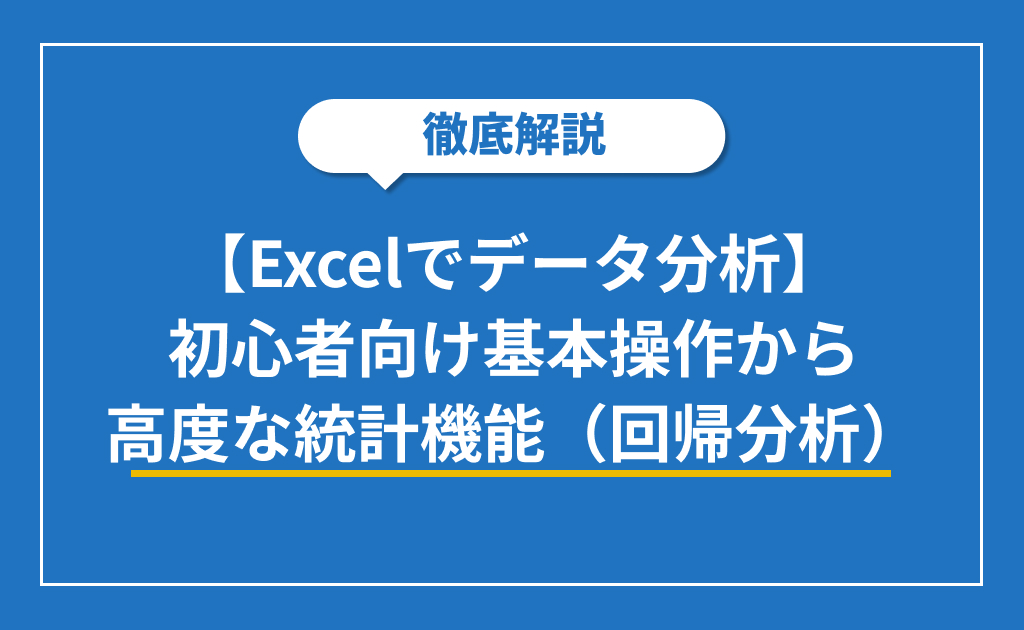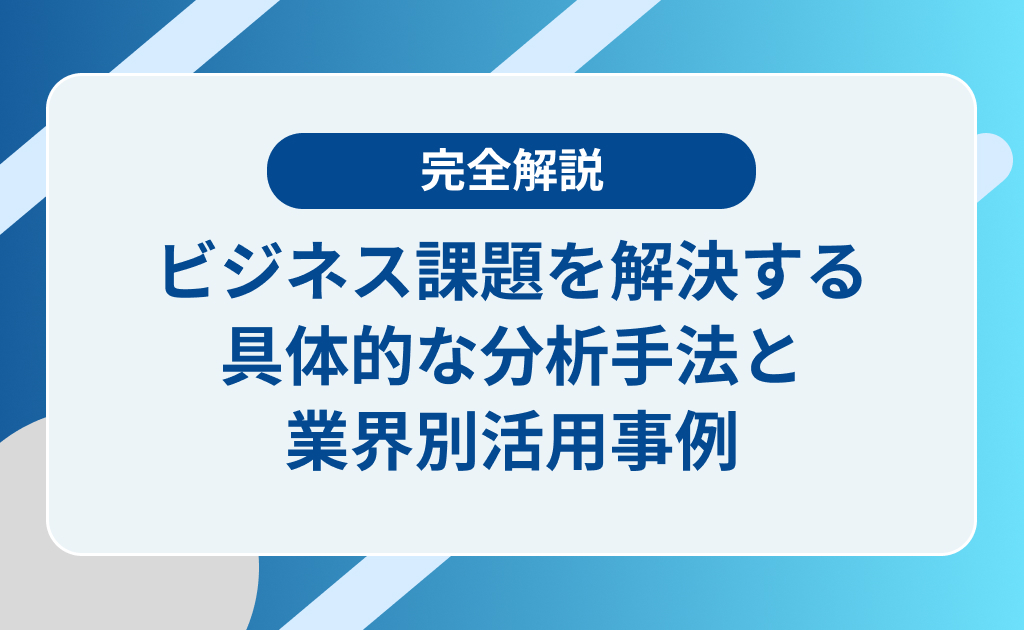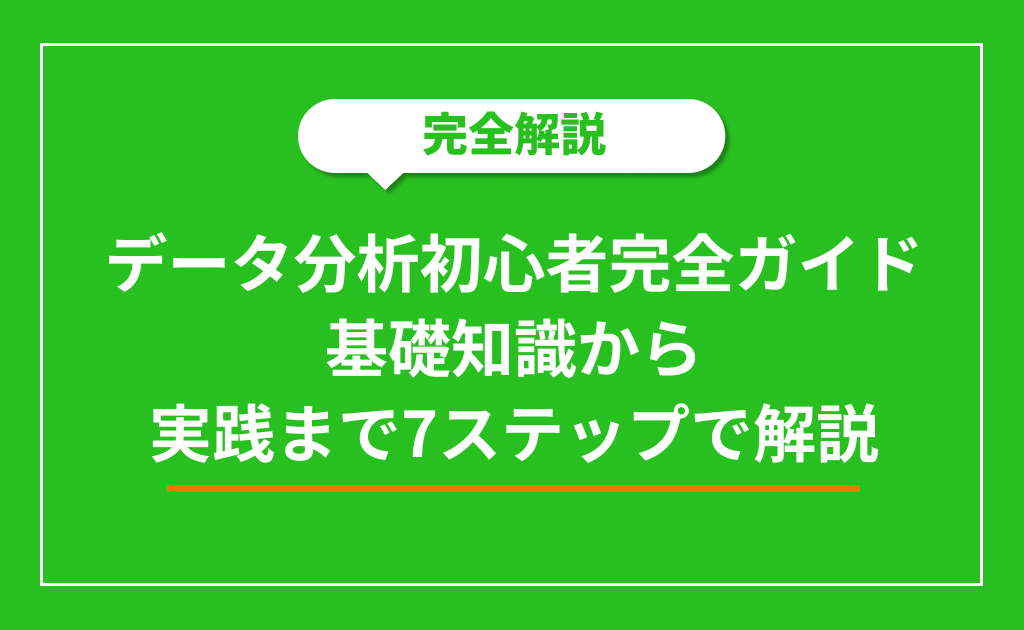データアナリストとデータサイエンティストの違いとは?役割・スキル・年収を徹底比較

「データアナリストとデータサイエンティストって何が違うの?」「どちらの方が年収が高い?」「自分にはどちらが向いている?」
データ分析を行う代表的な職種として、データアナリストとデータサイエンティストがあげられます。両職種の目的は、データ分析によってビジネス上の問題を解決することです。業務でデータの解析を行うことや統計学がベースとなることなど共通点が多く混同されがちですが、職務領域や必要とされるスキルなど明確な違いも存在しています。
大きく分けると、データアナリストはビジネス寄りの職種、データサイエンティストはシステム寄りの職種といえます。この違いを理解せずに転職すると、入社後のミスマッチに悩むことになりかねません。
本記事では、データアナリストとデータサイエンティストの違いを職務領域・必要スキル・年収・キャリアパスなどの観点から徹底的に比較し、あなたに最適な職種選択をサポートします。実際の業務における協働事例も交えながら、両職種の特徴を詳しく解説していきます。
データアナリストとデータサイエンティストの基本的な違い
データ分析が目的なのか手段なのか
両職種の大きな違いとして、データ分析が目的なのか手段なのかという点が挙げられます。
データアナリストは、データ分析してビジネス業務に役立てることが目的です。したがって、データ分析は業務を実現する手段にあたります。
データサイエンティストは、データの分析結果を業務に役立てることも大切ですが、データ分析のための仕組みを作ることにも重点を置いています。最適なデータ分析方法を構築することも、データサイエンティストがデータ分析を行う目的の一つです。
職種の定義と役割
データアナリストとは
データアナリストは、既存のデータを分析して、ビジネス上の問題解決や意思決定支援を行う専門家です。大量のデータから有用な情報を引き出し、事業部門からの要請に応じて、データの傾向や課題を明らかにし、レポートを作成します。
主な業務内容として、過去のデータを活用した現状分析や業績評価を行い、売上データの詳細な分析とレポート作成を通じてビジネスの実態を可視化します。また、顧客行動の分析から改善提案を導き出し、マーケティング施策の効果測定と最適化を行います。さらに、KPI・指標の設計と継続的な監視を通じて事業の健全性を確認し、経営層や事業部門が迅速な意思決定を行えるようダッシュボードの作成と運用を担当します。
# データアナリストの典型的な業務例
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# 売上データの月次分析
sales_data = pd.read_csv('monthly_sales.csv')
# 基本統計量の確認
print(sales_data.describe())
# トレンド分析
monthly_trend = sales_data.groupby('month')['sales'].sum()
plt.figure(figsize=(12, 6))
monthly_trend.plot(kind='line')
plt.title('Monthly Sales Trend')
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Sales Amount')
plt.show()
# 施策効果の測定
campaign_effect = sales_data.groupby('campaign_type')['conversion_rate'].mean()
print("キャンペーン別コンバージョン率:")
print(campaign_effect.sort_values(ascending=False))データサイエンティストとは
データサイエンティストは、統計学・機械学習・プログラミングを駆使して、データから新しい価値を創造する専門家です。予測モデルの構築や機械学習アルゴリズムの開発など、高度な分析技術を用いてデータから新たな価値を創出します。
その業務は多岐にわたり、予測モデルの構築や機械学習アルゴリズムの開発を通じて、将来の売上予測や顧客行動の予測を可能にします。ビジネス課題に対してデータの活用方法を提案し、未来予測や最適化といった高度な分析を実施します。また、新しい施策の効果を科学的に検証するためのA/Bテストの設計と統計的検証を行い、常に最新の技術動向を追いながら新しい分析手法の研究・開発に取り組みます。さらに、大規模データを効率的に処理するためのデータパイプラインの設計も重要な業務の一つです。
# データサイエンティストの典型的な業務例
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
import joblib
# 売上予測モデルの構築
def build_sales_prediction_model(data):
# 特徴量エンジニアリング
features = data[['season', 'promotion_budget', 'customer_count',
'avg_temperature', 'competitor_price']]
target = data['sales']
# 学習・テストデータの分割
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
features, target, test_size=0.2, random_state=42)
# モデルの訓練
model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
# 予測精度の評価
y_pred = model.predict(X_test)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
print(f"RMSE: {rmse:.2f}")
print(f"R²: {r2:.3f}")
# モデルの保存
joblib.dump(model, 'sales_prediction_model.pkl')
return model
# 交差検証による性能評価
cv_scores = cross_val_score(model, features, target, cv=5,
scoring='neg_mean_squared_error')
print(f"Cross-validation RMSE: {np.sqrt(-cv_scores.mean()):.2f}")職務領域から見る違い
データアナリストとデータサイエンティストはいずれもデータの分析や可視化を行います。しかし、職種領域が異なるため、データ分析に用いる技術や取り扱うデータの傾向などが違います。
データアナリストの職務領域
データアナリストは、統計学を用いてデータの分析や可視化を行います。データアナリストが扱うデータは多量になる傾向があり、一見すると関連性がなさそうなデータを集め、ビジネスの意思決定を行える形にデータを分析・可視化します。
データアナリストが用いるデータは主に、リレーショナルデータベースに保存できるような構造化データです。統計学を用いて、構造化データを人が理解できる形に分析し、統計学の専門家でなくとも理解できるような説明をします。
データサイエンティストの職務領域
データサイエンティストは、データアナリストよりも高度な分析を行う職種です。データアナリストが基本的な統計学を用いるのに対し、データサイエンティストは主に機械学習を用います。機械学習を用いて、データから将来を予測したり、音声や画像などの非構造化データを分析したりします。
機械学習のアルゴリズムの選択やパラメーターのチューニング、結果の分析などもデータサイエンティストの仕事です。
必要とされるスキルの違い
共通して必要なスキル
両職種に共通して必要なスキルも多く、まずはこちらから習得していくのがおすすめです。基礎となるのは大学教養レベルの数学の知識で、統計学においては記述統計、推測統計、多変量解析などの理解が不可欠です。プログラミングスキルとしてはPythonやR、SQLの習得が必須で、さらにHadoopやSparkなどのデータ分析基盤の構築スキルも身につける必要があります。また、マーケティングなどのビジネススキルも、分析結果をビジネス価値に変換する上で重要です。
各職種で特に求められるスキル
| スキル領域 | データアナリスト | データサイエンティスト |
|---|---|---|
| プログラミング | SQL中心、Python/R基礎VBA、Excel関数 | Python/R上級、複数言語TensorFlow、Keras等 |
| 統計学 | 記述統計、推測統計多変量解析 | ベイズ統計、時系列分析高度な統計モデリング |
| 機械学習 | 基本的な理解 | 教師あり学習、教師なし学習深層学習、強化学習 |
| 分析ツール | Excel、Tableau、PowerBISAS、BIツール | Jupyter、MLflowカスタム分析環境構築 |
| ビジネススキル | プレゼンテーションレポート作成、提案力 | 技術的コンサルティングシステム設計提案 |
データアナリストは基本的な統計学を頻繁に用いるので、SASやExcel、BIツールなどのソフトウェアの使用スキルが必要です。また、企業の担当者とコミュニケーションを取る場合もあるため、一般的なコンサルタントに求められる提案力やヒアリングスキル、資料の作成能力やプレゼンテーションスキルも必要となります。
データサイエンティストはAIや機械学習をデータ分析に頻繁に用いるため、AIや機械学習におけるアルゴリズム構築や分析モデルへの知見が求められます。データアナリストに比べるとエンジニア寄りの職種になるので、プログラミングやデータベース、統計学的手法をコンピューターで実現するスキルを深めていく必要があります。
具体的な事例で見る仕事内容の違い
実際の業務において、データアナリストとデータサイエンティストがどのように異なるアプローチで問題解決にあたるのか、具体的な事例を通じて解説します。
事例1: ECサイトにおける商品レコメンデーション
データアナリストのアプローチ:
過去の購買データを分析し、商品の購買傾向や顧客セグメントごとの嗜好を明らかにします。その結果をもとに、マーケティング施策の改善案を提案します。
-- 顧客セグメント別の購買傾向分析
SELECT
customer_segment,
product_category,
COUNT(DISTINCT customer_id) as customer_count,
SUM(purchase_amount) as total_sales,
AVG(purchase_amount) as avg_purchase
FROM customer_purchases
WHERE purchase_date >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 3 MONTH)
GROUP BY customer_segment, product_category
ORDER BY customer_segment, total_sales DESC;データサイエンティストのアプローチ:
購買データだけでなく、閲覧履歴や検索履歴なども含めた大規模データを用いて、機械学習モデルを構築。このモデルを用いて、個々の顧客に最適な商品レコメンデーションを行うシステムを開発します。
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
import pandas as pd
# 複数のデータソースを統合
def create_recommendation_model(purchase_data, browsing_data, search_data):
# 特徴量エンジニアリング
features = pd.merge(purchase_data, browsing_data, on='customer_id')
features = pd.merge(features, search_data, on='customer_id')
# モデル構築
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
features, target, test_size=0.2, random_state=42
)
model = RandomForestClassifier(n_estimators=200)
model.fit(X_train, y_train)
return model事例2: 製造業における品質管理
データアナリストのアプローチ:
製造ラインから収集された品質データを分析し、不良品の発生率や原因を特定します。分析結果をもとに、品質管理プロセスの改善点を提案します。
データサイエンティストのアプローチ:
品質データに加え、設備のセンサーデータや環境データなども分析に取り入れます。機械学習を用いて、不良品の発生を事前に予測するモデルを構築し、リアルタイムで品質管理を行うシステムを開発します。
事例3: 金融機関における与信管理
データアナリストのアプローチ:
顧客の属性データや取引履歴を分析し、与信リスクの高い顧客セグメントを特定します。その情報をもとに、与信基準の見直しを提案します。
データサイエンティストのアプローチ:
顧客データに加え、外部の経済指標や社会情勢なども考慮に入れた機械学習モデルを構築。このモデルを用いて、個々の顧客の与信リスクをスコアリングし、リスクに応じた与信管理を自動化します。
データアナリストとデータサイエンティストの協働
ここまで紹介した通り、データアナリストとデータサイエンティストは、互いの強みを活かし、協力することでより大きな成果を生み出すことができます。
協働のパターン
両職種の協働にはいくつかのパターンがあります。まず、発見と深堀りの連携では、データアナリストが日常的な分析から発見した課題や異常を、データサイエンティストが高度な分析手法で深堀りし、より根本的な原因や効果的な解決策を導き出します。
次に、実装と活用の分担では、データサイエンティストが機械学習や高度な統計手法を用いて新たな知見や予測モデルを開発し、データアナリストがその結果をビジネスの文脈で解釈し、実際の施策やアクションにつなげる役割を担います。
そして、データ文化の醸成においては、両者が協力してデータ活用の文化を組織全体に浸透させ、データ駆動型の意思決定を推進します。このような協働により、組織全体のデータリテラシーが向上し、より効果的なビジネス改善が可能になります。
業務内容・責任範囲の詳細比較
データアナリストの典型的な1日
データアナリストの一日は、朝会でのKPI確認から始まります。前日の売上、アクティブユーザー数、ARPUなどの主要指標をSQLクエリで取得し、ビジネスの健全性を確認します。
-- 前日の主要KPIを確認
SELECT
date,
SUM(revenue) as daily_revenue,
COUNT(DISTINCT user_id) as daily_active_users,
SUM(revenue) / COUNT(DISTINCT user_id) as arpu
FROM user_transactions
WHERE date = CURRENT_DATE - 1
GROUP BY date;午前中は主に月次レポートの作成に取り組みます。売上トレンドの分析、顧客セグメント別の成果測定、前月との比較分析を行い、経営層向けのサマリーを作成します。この際、単なる数値の羅列ではなく、ビジネスの文脈で解釈したインサイトを提供することが重要です。
午後はマーケティングチームとの会議があり、キャンペーン効果の分析結果を発表し、次回施策の提案を行います。A/Bテストの結果を共有し、データに基づいた意思決定をサポートします。その後、営業チームからの急な分析依頼や顧客からの問い合わせ調査など、アドホックな分析業務に対応し、一日の最後にはダッシュボードの更新・メンテナンスを行います。
データサイエンティストの典型的な1日
データサイエンティストの一日は、研究論文や技術記事のキャッチアップから始まります。朝の1時間は最新の機械学習手法や業界動向の調査に充て、常に技術の最前線にキャッチアップすることが重要です。
午前中の10時から12時にかけては、モデル開発や実験に集中します。
# 新しい特徴量を追加した予測モデルの検証
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
# ハイパーパラメータの最適化
param_grid = {
'n_estimators': [100, 200, 300],
'learning_rate': [0.01, 0.1, 0.2],
'max_depth': [3, 5, 7]
}
grid_search = GridSearchCV(
GradientBoostingRegressor(random_state=42),
param_grid, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error'
)
grid_search.fit(X_train, y_train)
print(f"Best parameters: {grid_search.best_params_}")
print(f"Best score: {grid_search.best_score_}")午後はデータエンジニアとの技術会議があり、データパイプラインの設計検討、モデル本番展開のアーキテクチャ議論、データ品質改善の技術的検討を行います。その後、実際にモデルの本番展開作業に取りかかり、Dockerコンテナの作成、APIエンドポイントの実装、監視・アラート設定などの技術的な作業を進めます。一日の最後には、最新の研究成果をまとめた論文執筆や、技術的な知見を共有するためのブログ作成を行います。
責任範囲の明確な違い
データアナリストの責任範囲は、主に現在の状況把握にあります。ビジネスにおいて何が起こっているかを正確に把握し、数値の異常や改善点を発見することで課題を特定します。その上で、具体的なアクションプランを提示し、実施された施策の成果を定量的に評価することで、PDCAサイクルを回していきます。
一方、データサイエンティストの責任範囲は、未来予測と新しい価値創造にあります。機械学習モデルを構築して何が起こるかを予測し、これまでにない分析手法を開発することで新たなビジネス機会を創出します。また、分析を自動化・効率化するシステムを構築し、新しい技術・手法の研究と実装を通じて、組織のデータ活用能力を向上させます。
年収・待遇の比較
年収分布の詳細分析
2024年の調査データによると、データアナリストの平均年収は約718万円、データサイエンティストの平均年収は約877万円となっています。技術的な知見が多く必要とされる分、データサイエンティストの年収が若干高い傾向にあります。
データアナリスト年収データ(2024年調査):
| 経験年数 | 平均年収 | 年収レンジ | 主な企業例 |
|---|---|---|---|
| 0-2年 | 450万円 | 350-600万円 | 中小企業、スタートアップ |
| 3-5年 | 580万円 | 450-750万円 | 大手事業会社 |
| 6-10年 | 720万円 | 600-900万円 | 外資系、コンサル |
| 10年以上 | 850万円 | 700-1200万円 | 管理職、フリーランス |
データサイエンティスト年収データ(2024年調査):
| 경험年数 | 平均年収 | 年収レンジ | 主な企業例 |
|---|---|---|---|
| 0-2年 | 550万円 | 400-750万円 | テック企業、研究所 |
| 3-5年 | 750万円 | 600-1000万円 | GAFAM、金融 |
| 6-10年 | 950万円 | 800-1400万円 | 外資系テック、コンサル |
| 10年以上 | 1200万円 | 1000-2000万円 | テックリード、独立 |
年収差が生まれる理由
両職種の年収差にはいくつかの理由があります。まず、技術的専門性の違いが挙げられます。データサイエンティストは機械学習や深層学習など、より高度な技術スキルが求められるため、希少価値が高く評価されます。次に、ビジネスインパクトの違いも重要な要因です。データサイエンティストが構築する予測モデルや最適化アルゴリズムは、数億円規模の事業価値を生み出すことがあり、その貢献度が年収に反映されます。さらに、転職市場での需給バランスも大きく影響しています。データサイエンティストの供給が需要に対して不足しているため、企業間の人材獲得競争が激しく、年収が高く設定される傾向があります。
必要スキル・学習難易度の詳細
スキル習得の学習時間比較
データアナリストになるための学習時間:
データアナリストになるためには、基礎スキルと実践スキルの両方を習得する必要があります。基礎スキルの習得には総計300-500時間が必要で、Excel上級(50時間)、SQL基礎(100時間)、Python/R基礎(150時間)、統計学基礎(100時間)、BIツールであるTableau等(50時間)の学習が含まれます。
実践スキルについては、総計200-300時間の学習が必要で、業界知識の習得(100時間)、レポート作成スキル(50時間)、プレゼンテーションスキル(50時間)、ビジネス理解(100時間)が含まれます。これらのスキルは、実際の業務でデータ分析結果をビジネス価値に変換するために不可欠です。
データサイエンティストになるための学習時間:
データサイエンティストの場合、データアナリストよりも大幅に多くの学習時間が必要となります。基礎スキルの習得には総計600-1000時間が必要で、プログラミング上級(300時間)、統計学・数学(200時間)、機械学習基礎(200時間)、データベース・SQL(100時間)の習得が含まれます。
応用スキルについては、さらに500-800時間の学習が必要で、機械学習応用(300時間)、深層学習(200時間)、MLOps・システム設計(200時間)、研究・論文読解(200時間)が含まれます。これらの高度なスキルは、実際に予測モデルを構築し、運用するために不可欠です。
学習の順序と戦略
データアナリスト向け学習ロードマップ(6ヶ月):
データアナリストを目指す場合、6ヶ月の体系的な学習プランが効果的です。最初の2ヶ月で基礎固めを行い、Excel/スプレッドシートの高度な使い方をマスターし、SQLでのデータ抽出(SELECT、JOIN、GROUP BY)、統計学の基礎(平均、分散、相関)、Python/pandasの基礎を習得します。
3-4ヶ月目には実践力を向上させ、matplotlibやTableauを使ったデータ可視化、効果的なレポート作成スキル、ビジネス分析手法を学び、実データでの演習プロジェクトに取り組みます。最後の2ヶ月では専門性を確立し、業界特化知識、高度な分析手法、プレゼンテーションスキルを磨き、最終的にポートフォリオを完成させます。
データサイエンティスト向け学習ロードマップ(12ヶ月):
データサイエンティストの場合は12ヶ月の長期プランが必要です。最初の3ヶ月で基礎スキルとしてPythonプログラミング、統計学・数学、SQL・データベースを徹底的に学びます。続く3ヶ月では機械学習基礎として教師あり学習、教師なし学習、モデル評価・検証を習得します。
7-9ヶ月目には応用・専門分野として深層学習・ニューラルネットワーク、自然言語処理または画像認識、時系列分析または推薦システムなどの専門分野を選んで深く学びます。最後の3ヶ月では実践・システム化としてMLOps・モデル運用、実プロジェクト、ポートフォリオ作成・転職準備を行います。
キャリアパスと将来性
データアナリストのキャリアパス
データアナリストのキャリアパスには大きく分けて3つの路線があります。
1. スペシャリスト路線では、ジュニアアナリストからシニアアナリスト、リードアナリストを経て、最終的にチーフアナリストやコンサルタントとして専門性を極める道があります。専門分野としては、マーケティングアナリスト、ファイナンシャルアナリスト、プロダクトアナリスト、ビジネスアナリストなど、特定の業界や機能に特化した役割があります。
2. マネジメント路線では、シニアアナリストからアナリティクスマネージャー、アナリティクス部門長を経て、最終的にCDO(Chief Data Officer)として組織全体のデータ戦略を統括するポジションを目指します。
3. キャリアチェンジ路線では、データアナリストとして培ったスキルを活かして、コンサルタントとして経営コンサルティングを行ったり、プロダクトマネージャーとしてデータドリブンな商品開発を担当したり、事業企画として分析に基づく事業戦略立案を行うといった選択肢があります。
データサイエンティストのキャリアパス
データサイエンティストのキャリアパスも大きく3つの路線に分かれます。
1. 技術専門家路線では、ジュニアデータサイエンティストからシニアデータサイエンティスト、リードデータサイエンティストを経て、最終的にプリンシパルデータサイエンティストとして組織の最高峰の技術者となる道があります。この路線では、常に最新の技術動向をキャッチアップし、高度なモデル開発やアルゴリズム設計を担当します。
2. 研究開発路線では、シニアデータサイエンティストからリサーチサイエンティスト、研究開発部門長を経て、最終的にCTO(Chief Technology Officer)として組織全体の技術戦略を統括するポジションを目指します。この路線では、新しい技術の研究開発や特許取得、学会発表など、よりアカデミックな活動も含まれます。
3. 起業・独立路線では、フリーランスとして高単価での個人コンサルティングを行ったり、AI系スタートアップを創業して技術を活かした事業創造を行ったり、複数企業の技術顧問として活躍するといった選択肢があります。特に近年では、AI技術の発展に伴い、独立して活躍するデータサイエンティストが増えています。
データ分析人材の需要について
IPAが公開しているDX動向2024では、DXを推進する人材の量について「大幅に不足している」「やや不足している」と答えた日本企業は85.7%に上り、データ分析人材の深刻な不足が明らかになっています。さらにDX推進人材の中で最も不足している人材類型についてのアンケートでは、「データサイエンティスト」人材が2位の19.1%を占め、日本企業の課題となっています。
この調査においてデータサイエンティストという職種は「事業・業務に精通したデータ解析・分析ができる人材」と定義されており、データアナリストも同じグループに属すると考えられます。つまり、両職種ともに日本のDX推進において極めて重要な役割を担っており、企業からの需要が非常に高い状況です。
2024年3月に発表されたIDC Japanによる調査では、2024年の国内ビッグデータ/アナリティクス市場は2兆749億円に到達すると予測されています。市場の拡大はデータ分析人材の需要拡大を裏付けているといえます。
将来性の比較
両職種の将来性を比較すると、それぞれ異なる特徴が見えてきます。
データアナリストは、安定性の面で★★★★☆と高く、継続的なニーズが期待できます。成長性は★★★☆☆で着実な需要増が見込まれ、代替リスクは★★☆☆☆とAIによる一部自動化の可能性はあるものの、ビジネス理解とコミュニケーション能力の重要性から完全な代替は難しいと考えられます。
データサイエンティストは、安定性が★★★☆☆と技術変化への対応が必要な一方で、成長性は★★★★★と急速な市場拡大が期待されます。代替リスクは★☆☆☆☆と高度な専門性により安全で、むしろAI技術の発展をリードする立場としての価値が高まっています。
混同しやすい他の職種との違い
データアナリストとデータサイエンティスト以外にも、類似する職種があります。それぞれの違いを理解することで、より明確なキャリアパスを描くことができます。
データエンジニアとの違い
データエンジニアの仕事は主にデータ分析を行うための基盤構築です。データアナリストやデータサイエンティストはデータ分析のために技術を用いますが、データエンジニアは分析のための土台作りに技術を用いる職種といえます。
具体的には、データを収集して納めておくための器の構築、分析を行うプラットフォームの設計、データ収集と加工を行うETLパイプラインの構築などを担当します。データアナリストやデータサイエンティストがスムーズに分析を行えるよう、データインフラを整備する重要な役割です。
アクチュアリーとの違い
アクチュアリーは保険数理士とも呼ばれ、保険や企業年金などに関する統計データの分析・提案が主な仕事です。データアナリストと非常に類似する職種ですが、活躍分野が金融分野に限られるという違いがあります。
正式にアクチュアリーを名乗るためには、公益社団法人日本アクチュアリー会が運営する資格試験に合格する必要があります。
BIエンジニアとの違い
BIエンジニアは、BIツールの設計、開発やBIツールを用いたデータ分析と可視化によりビジネスにおける意思決定を支援するエンジニア職種です。BIツールを専門的に取り扱うことが、データアナリストやデータサイエンティストとの大きな違いとなります。
データアーキテクトとの違い
データアーキテクトはデータ分析のプロですが、直接手を動かして作業を行うというよりは広い視点から全体設計を行う職種です。データ分析の上流工程を担い、データ関連職種のキャリアアップの選択肢とされることが多い職業です。
求人・転職市場の動向
求人数と市場動向
2024年求人市場データ:
| 職種 | 求人数 | 前年比 | 平均応募倍率 | 未経験OK求人率 |
|---|---|---|---|---|
| データアナリスト | 12,000件 | +15% | 8.5倍 | 45% |
| データサイエンティスト | 8,100件 | +27% | 12.3倍 | 32% |
この数字から読み取れる重要なポイント:
データアナリスト:
- 求人数が多く、選択肢が豊富
- 未経験からの転職機会が多い
- 応募倍率が相対的に低く、転職しやすい
データサイエンティスト:
- 高い成長率で需要が急増
- 競争は激しいが、スキルがあれば高待遇
- 技術的なハードルが高い
企業タイプ別の求人傾向
データアナリスト求人:
| 企業タイプ | 求人割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事業会社 | 60% | 安定志向、業界知識重視 |
| コンサル | 25% | 高年収、激務 |
| スタートアップ | 15% | 幅広い経験、成長機会 |
データサイエンティスト求人:
| 企業タイプ | 求人割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| テック企業 | 45% | 最新技術、高年収 |
| 金融 | 30% | 高度な数学スキル要求 |
| 製造業 | 15% | IoT・製造データ特化 |
| コンサル | 10% | 戦略立案、クライアントワーク |
どちらがあなたに向いているか?診断チェック
適性診断フローチャート
以下の質問に答えて、あなたにどちらの職種が適しているかを判断してみましょう。
【技術志向 vs ビジネス志向】
質問1: 新しい技術を学ぶことと、ビジネス課題を解決することのどちらにより興味がありますか?
A) 新しい技術を学ぶことの方が楽しい → データサイエンティスト寄り
B) ビジネス課題を解決することの方が楽しい → データアナリスト寄り
【コミュニケーション スタイル】
質問2: 理想的な働き方はどちらですか?
A) 技術チームとの深い議論や研究開発 → データサイエンティスト寄り
B) 様々な部署の人との協業やプレゼンテーション → データアナリスト寄り
【学習への取り組み方】
質問3: 困難な技術的課題に直面したとき、どう感じますか?
A) 興奮する・楽しくなる → データサイエンティスト寄り
B) 必要であれば取り組むが、できれば避けたい → データアナリスト寄り
【キャリア目標】
質問4: 10年後の理想的なポジションは?
A) 技術のエキスパートとして認められたい → データサイエンティスト寄り
B) ビジネスに大きな影響を与えるマネージャーになりたい → データアナリスト寄り
より詳細な適性分析
データアナリストに向いている人の特徴
1. ビジネス感度が高い
データアナリストに向いている人は、売上や顧客の動向に敏感で、数値の変化を素早く察知できる人です。単に数値を見るだけでなく、「なぜそうなったのか」をビジネス的に説明できる能力が重要で、数字の裏にある人間の行動を理解したいという好奇心を持っている人が適しています。
2. コミュニケーション能力が高い
技術的でない上司や他部署のメンバーに対して、複雑な分析結果を分かりやすく伝える能力が求められます。例えば、「今月の売上が前月比10%減少した理由は、競合他社のキャンペーンが原因と考えられます。データを見ると、価格帯別の売上シェアが…」のように、専門的な分析をビジネス言語に翻訳して伝えるスキルが重要です。
3. 実用性重視
学術的な新しさよりも、実際に使える解決策を好む傾向があります。完璧な分析モデルを長時間かけて作るよりも、80%の精度で今すぐ使えるものの方が価値があると考え、スピード重視で意思決定をサポートすることを大切にします。
4. 継続的な改善が得意
一度作ったダッシュボードやレポートを継続的に改善し、月次レポートの質を少しずつ向上させていくことにやりがいを感じる人が適しています。既存の仕組みを最適化し、より効率的で価値のある分析プロセスを構築していくことが得意です。
データサイエンティストに向いている人の特徴
1. 技術的好奇心が強い
新しいアルゴリズムや論文に常に興味を持ち、最新の技術動向を追いかけることが苦にならない人が適しています。ただ使うだけでなく、「どうやって動いているのか」を深く理解したいという探求心を持ち、プログラミング自体が楽しいと感じる人に向いています。
2. 論理的思考力が高い
# 仮説検証のプロセスが自然にできる
"""
仮説: 顧客の購買パターンには季節性がある
↓
データ収集: 過去3年分の購買データ
↓
分析手法: 時系列分析、季節分解
↓
検証: 統計的有意性の確認
↓
結論: 仮説の採択/棄却
"""3. 抽象化思考が得意
具体的なビジネス課題を数学的な問題として捉えることができ、複雑な現実世界の現象を数式やアルゴリズムで表現することに長けています。また、様々なデータからパターンを見つけて一般化し、汎用的なソリューションを構築することが得意です。
4. 長期的視点
短期的な成果よりも、将来の価値を重視し、研究開発的なアプローチを好む傾向があります。今すぐ役立たなくても、将来的に大きなインパクトを与える可能性のある基盤技術の構築に興味を持ち、じっくりと時間をかけて高度なシステムを開発することにやりがいを感じます。
実際の転職成功事例
データアナリスト転職成功事例
事例1:営業 → データアナリスト(Aさん・28歳)
Aさんは法人営業として年収480万円で働いていましたが、数字を扱うことは得意でも、より分析的な仕事がしたいという思いから転職を決意しました。
6ヶ月の転職準備期間では、最初の2ヶ月でExcel VBAとSQL基礎を学び、3-4ヶ月目にPython/pandasと統計学基礎を習得し、最後の2ヶ月でTableauをマスターしながらポートフォリオを作成しました。
その結果、EC系スタートアップ企業のマーケティングアナリストとして年収580万円(+100万円)での転職に成功しました。成功要因は、営業経験から得た顧客理解力をアピールし、実際の営業データを分析した実践的なポートフォリオを作成し、技術だけでなく売上への貢献を重視したビジネス視点を持っていたことです。
事例2:経理 → ファイナンシャルアナリスト(Bさん・32歳)
Bさんは経理・財務で年収520万円でルーチンワークをこなしていましたが、より戦略的な仕事がしたいと考えて転職を決意しました。
既存の財務知識を活かしながら、統計検定2級とVBAエキスパートの資格を取得し、英語力もアピールポイントとして活用した結果、外資系金融機関のファイナンシャルアナリストとして年収680万円(+160万円)での転職に成功しました。専門知識の深化と資格取得が大きな成功要因となりました。
データサイエンティスト転職成功事例
事例3:システムエンジニア → データサイエンティスト(Cさん・29歳)
CさんはWebアプリケーション開発エンジニアとして年収550万円で働いていましたが、より数学的・統計的な仕事がしたいという強い思いからデータサイエンティストへの転職を目指しました。
12ヶ月の学習期間では、最初の3ヶ月で統計学と線形代数の基礎を固め、次の3ヶ月でscikit-learnを使った機械学習を習得し、その後3ヶ月でTensorFlowやPyTorchを使った深層学習を学び、最後の3ヶ月で実プロジェクトとKaggleコンペに参加しました。
その結果、AI系スタートアップの機械学習エンジニアとして年収750万円(+200万円)での転職に成功しました。成功要因は、プログラミングスキルという技術的基盤、Kaggleでの上位入賞という実績、そして自然言語処理分野での専門性を確立したことです。
事例4:研究者 → データサイエンティスト(Dさん・35歳)
Dさんは大学研究員として物理学の研究に従事し、年収450万円で働いていましたが、研究成果を実社会で活用したいという強い想いからデータサイエンティストへの転職を決意しました。
論文執筆や統計解析の研究経験、高度な数学・統計学の知識、そして複雑な課題への取り組み経験という問題解決力をアピールした結果、外資系テック企業のシニアデータサイエンティストとして年収900万円(+450万円)という大幅な年収アップでの転職に成功しました。アカデミックなバックグラウンドが大きな強みとなりました。
転職を成功させるための具体的ステップ
データアナリスト転職の場合
Step1:基礎スキルの習得(1-3ヶ月)
データアナリストへの転職を成功させるためには、まず基礎スキルの習得が不可欠です。ExcelやGoogle Spreadsheetの上級機能をマスターし、SQLでは基本的なSELECT文に加えてJOIN、GROUP BY、HAVINGなどの集計機能を使いこなせるようになる必要があります。また、統計学の基礎として平均、分散、相関、回帰分析などの概念を理解し、実務で活用できるレベルに到達することが目標です。
推奨学習方法:
-- 実践的SQL練習例
-- 売上分析クエリの作成
SELECT
EXTRACT(MONTH FROM order_date) as month,
product_category,
SUM(sales_amount) as total_sales,
COUNT(DISTINCT customer_id) as unique_customers,
SUM(sales_amount) / COUNT(DISTINCT customer_id) as avg_sales_per_customer
FROM sales_data
WHERE order_date >= '2024-01-01'
GROUP BY
EXTRACT(MONTH FROM order_date),
product_category
ORDER BY month, total_sales DESC;Step2:実践スキルの習得(3-5ヶ月)
基礎スキルを身につけた後は、より実践的なスキルの習得に進みます。PythonやRを使ったデータ分析、TableauやPower BIを用いたダッシュボード作成、レポートライティングやプレゼンテーションスキルなど、実務で即戦力となるための能力を磨いていきます。特に、分析結果をいかに分かりやすく伝えるかという点が重要です。
実践プロジェクト例:
# ECサイトの顧客分析プロジェクト
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# RFM分析の実装
def rfm_analysis(df):
# Recency: 最後の購入からの日数
# Frequency: 購入頻度
# Monetary: 購入金額
current_date = df['order_date'].max()
rfm = df.groupby('customer_id').agg({
'order_date': lambda x: (current_date - x.max()).days, # Recency
'order_id': 'count', # Frequency
'sales_amount': 'sum' # Monetary
})
rfm.columns = ['Recency', 'Frequency', 'Monetary']
# スコア化(1-5の5段階)
rfm['R_Score'] = pd.qcut(rfm['Recency'], 5, labels=[5,4,3,2,1])
rfm['F_Score'] = pd.qcut(rfm['Frequency'].rank(method='first'), 5, labels=[1,2,3,4,5])
rfm['M_Score'] = pd.qcut(rfm['Monetary'], 5, labels=[1,2,3,4,5])
# 顧客セグメンテーション
rfm['Segment'] = rfm['R_Score'].astype(str) + rfm['F_Score'].astype(str) + rfm['M_Score'].astype(str)
return rfmStep3:ポートフォリオ作成(5-6ヶ月)
転職活動の最終段階では、自分のスキルを証明するポートフォリオの作成が不可欠です。ポートフォリオには、実際のデータを使ったクリーニング事例、探索的データ分析(EDA)によるデータの特徴や傾向の発見、分析結果に基づく具体的なビジネス提案、そして継続的に監視できるダッシュボードなどを含め、実務での即戦力をアピールすることが重要です。
データサイエンティスト転職の場合
Step1:数学・統計学の基礎固め(1-4ヶ月)
データサイエンティストへの転職を成功させるためには、しっかりとした数学・統計学の基礎が必要です。線形代数では行列、ベクトル、固有値の概念を理解し、微積分では偏微分や勾配の計算ができるようになる必要があります。確率・統計ではベイズ統計や仮説検定の手法を習得し、最適化理論の基礎も押さえておくことが大切です。これらの知識は機械学習アルゴリズムを理解する上で不可欠です。
学習リソース:
# 統計学の実装練習例
import numpy as np
import scipy.stats as stats
from scipy import optimize
# ベイズ推定の実装
def bayesian_ab_test(control_conversions, control_trials,
treatment_conversions, treatment_trials):
"""
A/Bテストの結果をベイズ統計で分析
"""
# 事前分布(ベータ分布)
alpha_prior, beta_prior = 1, 1
# 事後分布
alpha_control = alpha_prior + control_conversions
beta_control = beta_prior + control_trials - control_conversions
alpha_treatment = alpha_prior + treatment_conversions
beta_treatment = beta_prior + treatment_trials - treatment_conversions
# 事後分布からサンプリング
control_samples = np.random.beta(alpha_control, beta_control, 10000)
treatment_samples = np.random.beta(alpha_treatment, beta_treatment, 10000)
# 改善確率の計算
improvement_prob = np.mean(treatment_samples > control_samples)
return improvement_prob, control_samples, treatment_samplesStep2:機械学習・深層学習(4-8ヶ月)
数学・統計学の基礎を身につけた後は、機械学習と深層学習の学習に進みます。まず教師あり学習の回帰や分類から始め、次に教師なし学習のクラスタリングや次元削減を学びます。その後アンサンブル学習を理解し、深層学習のニューラルネットワークに進みます。最終的にはNLP、画像認識、時系列分析などの特化分野から自分の興味、目指す業界に合わせて選択し、専門性を磨いていきます。
Step3:実装・運用スキル(8-12ヶ月)
データサイエンティストとしての最終段階では、作成したモデルを実際に運用するスキルが求められます。MLOpsによるモデルの継続的な運用、DockerやKubernetesを用いたデプロイ、AWS、GCP、Azureなどのクラウドプラットフォームの活用、Sparkなどを使った大規模データ処理のスキルを身につけることで、実務で即戦力となるデータサイエンティストを目指します。
# MLOpsの実装例
import mlflow
import mlflow.sklearn
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
# 実験管理
with mlflow.start_run():
# モデル訓練
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
# 予測・評価
predictions = model.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
# メトリクスとモデルの記録
mlflow.log_param("n_estimators", 100)
mlflow.log_metric("accuracy", accuracy)
mlflow.sklearn.log_model(model, "random_forest_model")データアナリストとデータサイエンティストにおすすめの資格
データアナリストやデータサイエンティストを目指すにあたっての学習では、資格の取得がおすすめです。両職種ともに必須の資格はありませんが、資格取得に向けての学習では体系的かつ効率的に知識を身につけることができます。
統計検定
統計検定は、日本統計学会の認定する統計学に特化した資格試験で、レベルごとにさまざまな区分があります。統計検定2級はデータアナリスト向けの基礎レベルで、統計検定準1級は実務で活用できる応用レベルです。また、統計検定データサイエンス基礎はデータサイエンス入門者向け、統計検定データサイエンス発展は実践的なスキル習得を目的としています。
プログラミング関連資格
Python 3 エンジニア認定試験は、基礎試験でPythonの基本文法を、実践試験で実務で使える応用スキルを、データ分析試験でデータ分析に特化したスキルを評価します。段階的にスキルを証明できるため、転職活動でもアピールポイントとなります。
データベース関連資格
ORACLE MASTERは商用データベースの知識とSQLを体系的に学べる資格で、データベーススペシャリスト試験はより高度なDB設計・運用スキルを証明します。データ分析業務ではSQLが必須スキルとなるため、これらの資格は非常に有用です。
データサイエンティスト検定
データサイエンティストのための専門資格で、ビジネス力、データサイエンス力、データエンジニアリング力の3つの軸で評価されます。総合的なスキルセットを証明できるため、データサイエンティストとしてのキャリアを本格的にスタートさせる際に取得を検討する価値があります。
よくある質問と回答
Q1: データアナリストとデータサイエンティストの違いは何ですか?
A: データアナリストとデータサイエンティストの違いは、主に職務領域です。データアナリストはデータ分析の結果を業務に活用することに重点が置かれているのに対し、データサイエンティストはデータを分析する仕組みの構築に重点を置いています。
Q2: どちらが将来性がある?
A: 両職種とも将来性はありますが、性質が異なります。
データアナリスト:
- 安定した需要の継続
- AIによるツールの進化で効率化が進む
- より戦略的・コンサルティング的な役割への進化
データサイエンティスト:
- 急速な市場拡大による需要増
- 新技術への継続的な対応が必要
- 高い専門性による希少価値の維持
Q3: 年収はどちらが高い?
A: 2024年の調査データによると、データアナリストの平均年収は約718万円、データサイエンティストの平均年収は約877万円です。一般的にはデータサイエンティストの方が高年収ですが、個人の適性と努力次第で変わります。
重要なのは、自分に合った職種を選ぶことです。自分に合わない職種を選ぶと、長期的に年収が伸び悩む可能性があります。
Q4: 未経験からならどちらが転職しやすい?
A: データアナリストの方が転職しやすいと言えます。
理由:
- 求人数が多い:選択肢が豊富
- 未経験OK求人の割合が高い:45% vs 32%
- 学習のハードルが相対的に低い:必要スキルが明確
- 実務経験を活かしやすい:営業、マーケティング等の経験が直接活用可能
Q5: 文系出身でも大丈夫?
A: どちらも文系出身者が活躍していますが、アプローチは異なります。
データアナリスト:
- ビジネス理解力や文章力は文系の強み
- 数学への苦手意識も克服可能なレベル
- コミュニケーション能力が重要で文系有利
データサイエンティスト:
- 数学・統計学の学習に時間をかける必要
- プログラミングスキルの習得が重要
- 論理的思考力があれば文系でも十分可能
Q6: データサイエンティストに向いている人の特徴は?
A: データサイエンティストは、データサイエンスという手法を用いたデータの分析を用いるエンジニア職種であり、そのための仕組みの構築を担います。数学、統計学、機械学習などの知見を組み合わせて構築することが求められるため、論理的な思考が得意な人は向いているといえます。
自分に合った役割を見極めよう
データアナリストとデータサイエンティストは、どちらもデータを扱う重要な職種です。両職種の目的は「データ分析によってビジネス上の問題を解決すること」で共通していますが、アプローチや必要スキル、キャリアパスには明確な違いがあります。
データアナリストとデータサイエンティスト、どちらを目指すべき?
どちらを目指すか迷っている方は、まず双方の職種の特徴を押さえた上で、自分の適性ややりたいことから検討すると良いでしょう。
データアナリストは、ビジネススキルが重視される傾向にあり、コンサルタントのような役割を求められることが多いです。
データサイエンティストは、高度な分析技術を使いこなして問題解決をするような、エンジニアとしての役割を求められることが多い傾向にあります。
どちらの職種を目指すにしても高度な知識やスキルが求められるため、自分の目的に合ったほうを選ぶことでモチベーションの維持にもつながるでしょう。
選択のためのチェックポイント
データアナリストを選ぶべき人:
✅ ビジネス課題の解決により興味がある
✅ 多様な人とのコミュニケーションが得意
✅ 実用的で即効性のある解決策を好む
✅ 比較的短期間で転職したい
✅ 安定した職種を求める
データサイエンティストを選ぶべき人:
✅ 新しい技術の学習に興奮を感じる
✅ 数学的・論理的思考が得意
✅ 長期的な研究開発に興味がある
✅ 高年収を狙いたい
✅ 技術的な深さを追求したい
まとめ
データアナリストとデータサイエンティストの違いは、職務領域と用いる技術です。
データアナリストは主にデータの解析と洞察を提供し、基本的な統計手法やデータツールを活用します。対照的に、データサイエンティストは予測モデルの構築や高度な機械学習技術を駆使して課題にアプローチします。
これらの職種への転職を目指す際には、両者の違いを意識して、自身の特性とあった職種を選ぶことが重要です。自分がしたい仕事が、データ分析の活用なのか、データ分析の仕組み作りを含めた業務なのか、スキルの習得とともに見極めましょう。
自分の強みや興味、将来のキャリアビジョンを考慮して、どちらの職種が自分に合っているかを見極めることが大切です。
データサイエンティストを目指す方は、統計学や機械学習の深い知識を身につけ、プログラミングスキルを磨くことが求められます。一方、データアナリストを目指す方は、ビジネス知識を深め、データ可視化や問題解決能力を高めることが重要です。どちらの職種もデータを通じてビジネス価値を創出する重要な役割を担っており、自分の強みを活かせる道を見つけることで、データの力でビジネスに貢献できる人材を目指しましょう。