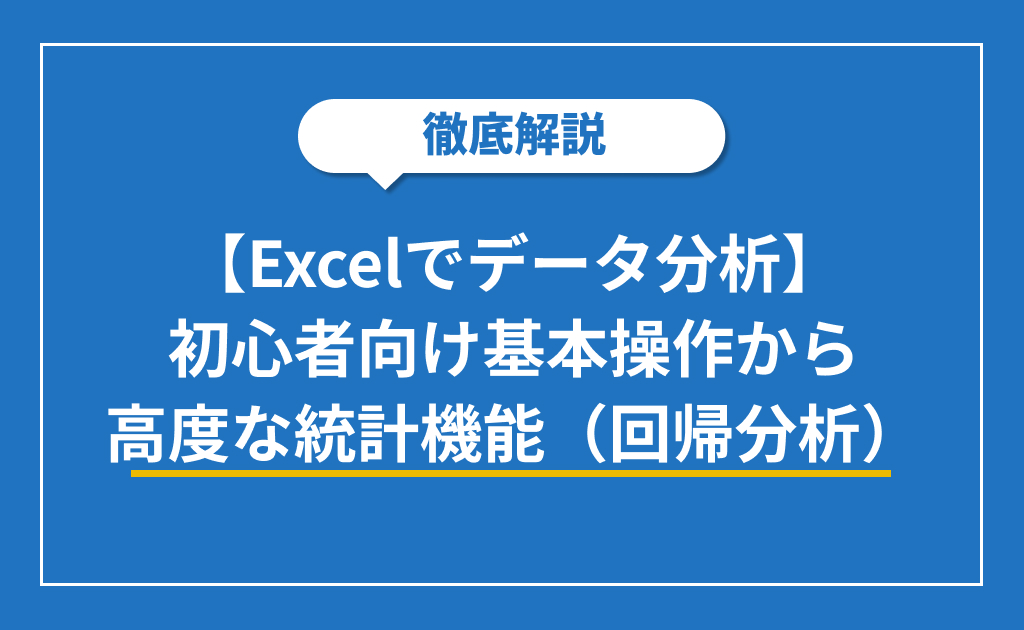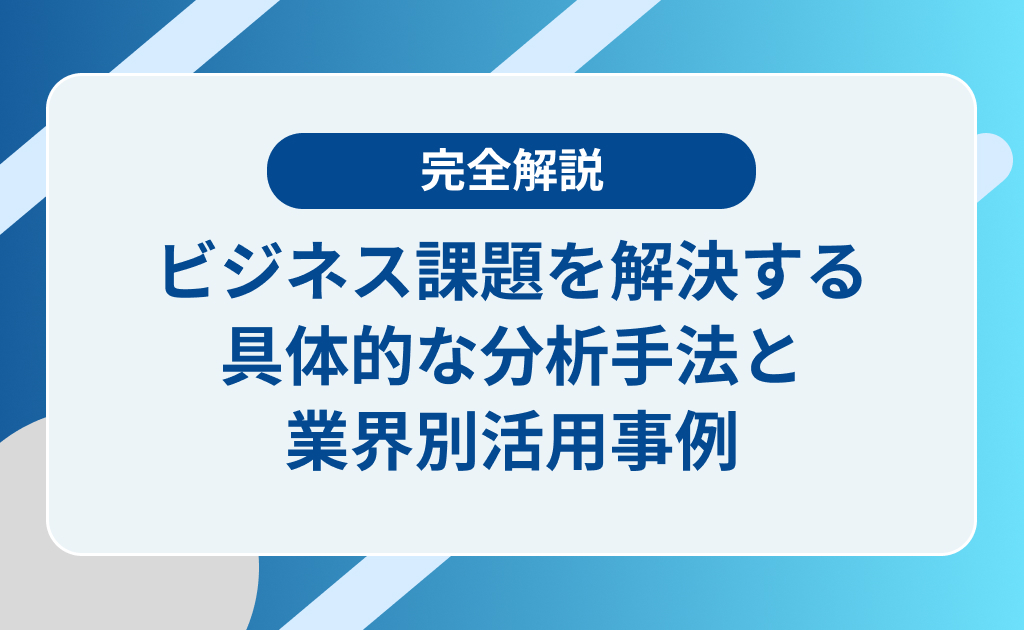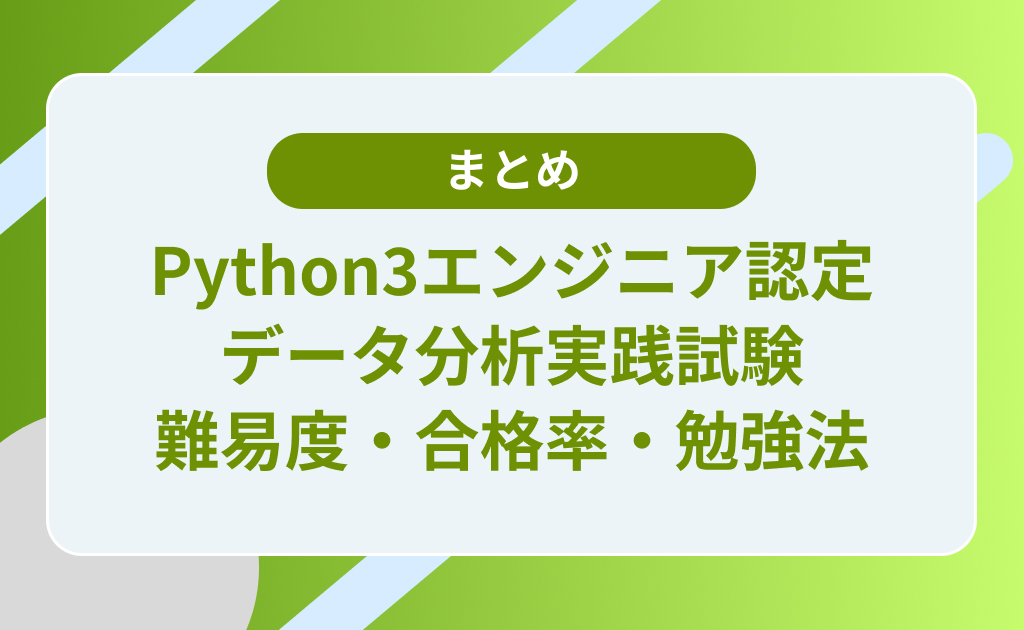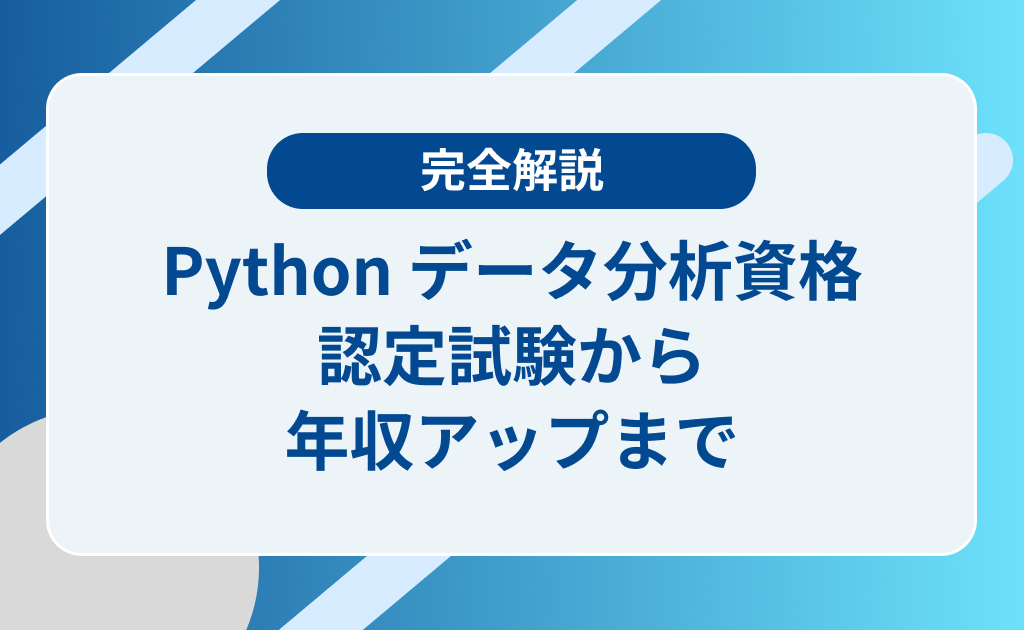データサイエンティスト資格完全ガイド!取得すべき資格と年収への影響

最近、ビッグデータの利活用の重要性が高まる中で、データサイエンティストという職業が注目されるようになりました。
「データサイエンティストとして就職・転職するために、データサイエンティストに関連する資格を取得したいと考えているけど、どれを選べばいいんだろう?」
「そもそも、データサイエンティストに資格は必要なの?」
「資格を取れば本当に年収アップにつながるの?」
こんな疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は私も、データサイエンティストを目指し始めた頃、まったく同じことで悩んでいました。統計検定、Python認定、AWS認定…次から次へと新しい資格の情報が入ってきて、「全部取らないとダメなの?」と途方に暮れたものです。
しかし、実際にこの業界で働いてみて分かったことがあります。それは、資格は「目的」ではなく「手段」であるということです。
結論から言うと、既にデータサイエンティストとして働いている場合、資格を取得する必要性は低いといえます。資格取得のために時間をかけるより実務経験を積む方が、キャリアアップにつながる可能性が高いからです。
しかし、未経験からデータサイエンティストとして就職したい場合、資格は有利な武器になります。資格を取得しておくことで、自分がどのようなスキルを有しているかを客観的に説明できるからです。
本記事では、私自身の経験や、実際に資格を活用して転職に成功した仲間たちの事例を交えながら、データサイエンティスト向けの主要な資格について詳しく解説します。
資格を取得するメリット
データサイエンティストに関連する資格を取得するメリットを2つ紹介します。
(1)データサイエンスに関する知識を体系的に身につけられる
資格取得のための勉強を通じて、データサイエンスに関する知識を体系的に身につけられます。
独学で学習を進めようとすると、どの分野から始めるべきか、どのような順序で学ぶべきかわからなくなってしまうこともあるでしょう。私も最初は「Pythonから始めるべき?それとも統計学?」と迷走していました。
一方、資格には出題範囲が設定されているので、出題範囲に沿って学習を進めていくことで、データサイエンスの知識を体系的に習得することが可能です。
実際、私が統計検定2級の勉強を始めたとき、「あ、今まで点でしか理解していなかった知識がつながった!」という瞬間が何度もありました。例えば、なんとなく使っていたp値の意味が深く理解できたり、機械学習の評価指標の統計的な背景が分かったりしたのです。
(2)就職・転職活動に役立つ
未経験からデータサイエンティストに就職・転職する際に資格は役立ちます。自分にどれだけのスキルがあるかを客観的に自己分析できるからです。この自己分析を通じて、今の自分には何ができるのか、また、これからどのような知識やスキルを身につければよいかがわかります。
また、資格は採用担当者へのアピールにもなります。未経験者でも、資格を取得していることで、どの程度の知識やスキルを身につけているかを採用担当者が客観的に判断できます。
私の友人で、営業職からデータサイエンティストに転職した人がいます。彼は「統計検定2級とPython認定を取得していたことで、面接で『本気度』が伝わった」と話していました。実際、書類選考の通過率も格段に上がったそうです。
データサイエンティスト関連の資格を選ぶ際の注意点
取得する資格を選ぶ際には以下の2つに注意しましょう。
(1)自分のレベルに合うか確認する
データサイエンスに関する資格は、初心者向けから上級者向けまでさまざまなものがあります。自分の現在のスキルや知識のレベルを正確に把握し、それに合った資格を選ぶようにしましょう。
初学者が最初から高難度の上級者向け資格にチャレンジすると、何度受けても合格できず、挫折してしまうかもしれません。私も最初、いきなり統計検定1級に挑戦しようとして、過去問を見た瞬間に心が折れた経験があります…。
(2)自分の目的に合うか確認する
資格試験の目的は、データサイエンスの基礎に関する理解度を測るため、ビジネスにおけるデータサイエンス利活用の能力を評価するため、プログラミングスキルを測るためなどさまざまです。そのため、取得する資格を選ぶ際は自分の目的に合っているか確認した上で選ぶことが大切です。
例えば、データサイエンティストとしてビジネスの現場で活躍したいなら、実践的なスキルが身につくデータ分析実務スキル検定(CBAS)を選ぶことをおすすめします。
データサイエンティスト関連の初学者向けの資格
データサイエンティスト関連の資格の中から、初学者向けの資格を4つ紹介します。
(1)データサイエンティスト検定 リテラシーレベル
データサイエンティスト検定 リテラシーレベル(以下DS検定)は、一般社団法人データサイエンティスト協会(以下DS協会)が実施している資格です。
DS協会では、データサイエンティストに必要なスキルをスキルチェックリストとして公表しています。このスキルチェックリストは以下の3つの領域に分かれています。
・データサイエンス力
情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知識を理解し使う力
・データエンジニアリング力
データサイエンスを意味のある形に使えるようにし実装・運用できるようにする力
・ビジネス力
課題背景を理解した上でビジネス課題を整理し解決する力
DS検定では、スキルチェックリストにあげられているスキルのうち最も基礎的なものを3つの領域からそれぞれ出題されます。そのため、データサイエンティストに必要な基礎知識を総合的に身につけられます。また、DS検定を受験することで、これからデータサイエンティストとしてスキルアップする際に、どのように学習を進めればよいのかわかります。
私も最初にDS検定を受験しましたが、「データサイエンティストってこんなにも幅広い知識が必要なんだ」と改めて実感しました。でも同時に、「これから何を学べばいいか」の道筋が見えたので、学習計画が立てやすくなりました。
(2)統計検定データサイエンス基礎(DS基礎)
統計検定は、一般財団法人統計質保証推進協会が実施しています。統計検定は、2011年から実施されており、どれだけ統計学を理解しているかが評価されてきました。
この統計検定に2019年からデータサイエンスに特化した試験が新たに始まりました。DS基礎はデータサイエンスに特化した統計検定の中で、最も簡単な試験です。
DS基礎は高校の数学、情報の分野から出題され、統計学の知識に加えて、Excelを用いたデータ分析、出力結果の解釈などが出題されます。
将来データサイエンティストとして活躍するために、まずはExcelを用いたデータ分析ができるようになりたいという方におすすめです。実際、多くの企業ではまだExcelが主力ツールなので、この資格で学ぶスキルは即戦力になります。
(3)G検定
G検定は一般社団法人日本ディープラーニング協会が実施している資格です。ディープラーニングの基本的な技術とその活用方法の理解が問われます。これからAIを勉強したい方だけでなく、AIをビジネスに活用したい方向けの資格です。
データサイエンティストはディープラーニングを用いた高度なデータ分析技術が求められます。G検定は、将来データサイエンティストになるために、まずはディープラーニングやAIに関する基礎知識を身につけたいという方におすすめです。
(4)データサイエンス数学ストラテジスト(中級)
データサイエンス数学ストラテジスト(MDS-S)は、公益財団法人日本数学検定協会が開催している資格です。MDS-Sでは、データサイエンスに必要な数学の知識が問われます。
MDS-S(中級)では、高校1年レベルの数学の問題が出題されます。データ利活用を推進するために、まずは数学の基礎を勉強したいという方は、受験してみましょう。
データサイエンティスト関連の中級者以上向けの資格
次に、中級者向けの資格を5つ紹介します。
(1)統計検定データサイエンス発展(DS発展)
統計検定データサイエンス発展(DS発展)は、前述したDS基礎を踏まえ、さらに高度な大学教養レベルのデータサイエンスの知識が問われます。
Excelでのデータ分析だけでなく、Python、Rを用いたより高度な分析、プログラミングスキル、大学教養レベルの線形代数、微分積分、統計学などが問われます。
(2)統計検定データサイエンスエキスパート (DSエキスパート)
統計検定データサイエンスエキスパート(DSエキスパート)は、DS発展を踏まえ、さらに高度な大学専門レベルの知識が要求されます。
難易度の高い、線形代数、微分積分、統計学、プログラミングスキル、AIの理解などが求められます。
(3)データサイエンス数学ストラテジスト(上級)
MDS-S(上級)は、MDS-S(中級)を踏まえ、より高度なデータサイエンスに関する数学の問題が出題されます。
高校までの数学に加え、大学初年度の線形代数、微分積分、統計学、機械学習・深層学習に使われている数学、プログラミングで使われる数学などが問われます。
(4)E資格
E資格は、一般社団法人ディープラーニング協会が実施している資格です。前述したG検定は一般向けの資格である一方、E資格はエンジニア向けの資格です。そのため、G検定レベルのディープラーニングの理解に加えて、ディープラーニングの実装スキルが試されます。
E資格を受験するには、ディープラーニング協会認定のプログラムを受講しなければなりません。このプログラムを通して、実際にプログラミングをしながらディープラーニングの勉強ができるので、AIを実際に実装する技術を習得できます。
(5)Python 3 エンジニア認定基礎試験
Python 3 エンジニア認定基礎試験は、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が実施している資格です。この試験では、Pythonで基本的な実装ができるスキルを評価されます。
Pythonとは、データサイエンスの分野で最も使用されているプログラミング言語です。これからデータサイエンティストになるためには、Pythonでプログラミングが書けなければなりません。これからプログラミングの勉強をする方は、Python3エンジニア認定基礎試験を通じてPythonを習得してもよいでしょう。
データサイエンティストの実務に直結する資格
貴重な時間を割いて資格取得の勉強に取り組むなら、ビジネスの現場で役立つ実践的なスキルを身につけたいという方もいらっしゃるでしょう。そのような方におすすめなのが、今多くの企業から注目されているデータ分析実務スキル検定(CBAS)です。
CBASと他の資格との違いは、他の資格が専門知識やテクニカルなスキルを重点的に評価するのに対し、CBASは、「実務に直結した能力を測る」ことを重視している点です。CBASは、ビジネスの現場で本当に役立つ実務能力を持つ人材を求めている企業から高い評価を受けていて、多くの企業が人材育成のツールとして取り入れています。
CBASには、以下の2つの種類があります。
(1)CBAS シチズン・データサイエンティスト級(Citizen級)
Citizen級は、ビジネスの現場に存在するデータを的確に活用して分析するスキルを評価する試験で、Excelでデータを整理したり、修正したりできる能力が問われます。Excelを活用したデータ分析のスキルは幅広い業務で活用できます。
Excelを使って業務に関する課題を分析し、新たな知見を得る力や課題を解決する力を養いたい人におすすめです。
(2)CBAS プロジェクトマネージャー級(PM級)
PM級は、組織横断的にデータ活用の推進をリードし、データ分析の専門家と経営陣の橋渡し役として機能するスキルを評価する試験です。データサイエンスに関する専門的な知識を持ちながら、ビジネスにも精通しているプロジェクトマネージャーは、今後、多くの企業で必要とされるでしょう。
DX関連のプロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーとして活躍したい方におすすめです。
私が取得して本当に役立った資格ベスト3
実際に私や同僚たちが取得して「これは取ってよかった!」と感じた資格を、リアルな体験談とともにご紹介します。
第1位:統計検定2級
「え、そんな基礎的な資格が1位?」と思われるかもしれませんが、これには理由があります。
私が統計検定2級を取得したのは、データサイエンティストになって1年目のことでした。それまでは「なんとなく」機械学習のコードを書いていましたが、統計検定の勉强を通じて初めて「なぜこの手法を使うのか」が理解できるようになったのです。
例えば、p値が0.05以下だと「有意差がある」と判断していましたが、その背景にある考え方を理解したとき、「今まで機械的に判断していたんだな」と気づきました。それ以降、分析結果の解釈が格段に深くなり、クライアントへの説明も説得力が増しました。
実際、転職活動でも「統計検定2級を持っています」と言うと、「基礎がしっかりしている」という評価をいただけることが多かったです。
第2位:AWS Machine Learning Specialty
2位は、クラウド系の資格です。正直、受験料が高くて(300ドル!)躊躇しましたが、取得後の効果は絶大でした。
私がこの資格を取得したのは、会社でAWSを使った機械学習基盤の構築プロジェクトが立ち上がったタイミングでした。資格の勉強を通じて学んだSageMakerの知識が、そのまま実務で活かせたんです。
さらに、この資格を持っていることで、社内でも「AWSの専門家」として認識されるようになり、重要なプロジェクトにアサインされる機会が増えました。年収も実際に100万円近くアップしたので、受験料の元は十分に取れました。
第3位:データサイエンティスト検定アソシエイトレベル
3位は、データサイエンティスト協会の検定です。この資格の良いところは、「データサイエンティストとして必要な知識を網羅的に学べる」ことです。
私は独学でデータサイエンティストになったので、知識に偏りがありました。プログラミングは得意でも、ビジネス課題の設定が苦手だったり…。この検定の勉強を通じて、自分の弱点が明確になり、バランスよくスキルを身につけることができました。
特に印象的だったのは、「データサイエンティストは技術だけじゃなく、ビジネス価値を生み出すことが重要」という考え方を学んだことです。それ以降、単に精度の高いモデルを作るだけでなく、「このモデルがビジネスにどう貢献するか」を常に考えるようになりました。
データサイエンティストの資格を取るべき人
データサイエンティストの資格を取るべき人として、以下が該当します。
1:未経験からデータサイエンティストとして転職したい人
2:学習意欲の継続・向上として資格取得を利用したい人
3:資格手当がもらえる企業に属している人
データサイエンティストに関連する資格は、キャリアの目的や、状況に応じてさまざまな価値を発揮します。未経験からの転職を目指す人にとってはスキルの証明手段となり、学習を継続したい人にはモチベーション維持に役立ちます。また、資格手当制度のある企業では報酬アップにもつながるため、積極的に活用したい選択肢です。
1:未経験からデータサイエンティストとして転職したい人
未経験からデータサイエンティストを目指す場合、資格は「学んだ証明」として非常に有効です。統計やプログラミング、データベースなどの基礎知識を体系的に学びながら、G検定やCBAS、統計検定などを取得することで、スキルと学習意欲を客観的にアピールできます。実務経験がない状態でも、資格があることで「ポテンシャル層」として採用対象になる可能性が高まり、選考通過率の向上や学習の方向性の明確化にもつながります。
2:学習意欲の継続・向上として資格取得を利用したい人
データサイエンスの学習は広範かつ長期的になりがちですが、資格を活用することで学習の区切りと達成感を得やすくなります。特にG検定や統計検定、データサイエンス数学ストラテジストなどは、段階的に難易度を上げながら知識を深めていけるため、学習のモチベーション維持に最適です。試験日という明確な目標があることで計画的に学習を進められ、習慣化の手助けにもなります。自己研鑽を可視化できる手段としても有効です。
3:資格手当がもらえる企業に属している人
企業によっては、G検定や統計検定、ORACLE MASTER、CBASなどの取得に対して資格手当や受験費用補助が支給される制度があります。このような制度を活用することで、実質的なコスト負担を抑えながらスキルアップを図ることができます。また、会社から評価されやすくなることで、キャリアパスの幅が広がる可能性もあります。報酬面と成長機会の両面を得られる制度があるなら、積極的に資格取得を目指すべきです。
おすすめの資格取得ロードマップ
未経験から始める場合(1年プラン)
私の知人で、営業職からデータサイエンティストに転職した人のロードマップを参考にご紹介します。
1-3ヶ月目:基礎固め
- 統計検定3級または2級
- 「まずは統計の基礎を固めることが大切。3級は簡単すぎると思ったら、いきなり2級でもOK」
4-6ヶ月目:実践スキル
- Python 3 エンジニア認定基礎試験またはデータサイエンティスト検定リテラシーレベル
- 「Pythonの基礎を学びながら、データサイエンス全体像を把握」
7-9ヶ月目:専門性強化
- G検定(AI・機械学習の基礎)
- 「面接でAIの知識を聞かれることが多いので、G検定は役立った」
10-12ヶ月目:転職活動
- ポートフォリオ作成と並行して転職活動
- 「資格だけでなく、実際にデータ分析したプロジェクトを見せることが重要」
すでに実務経験がある場合(高度資格へのチャレンジ)
実務経験が1-2年ある方は、以下のような高度な資格にチャレンジすることで、さらなるキャリアアップが期待できます。
統計検定準1級・1級
- より深い統計学の理解が求められる場面で差別化できる
- 「準1級を取得してから、分析の質が格段に上がった」という声多数
AWS/GCP/Azure のクラウド認定
- 実務でクラウドを使う機会が増えているため、需要が高い
- 「AWS Machine Learning Specialtyを取得後、プロジェクトリーダーに抜擢された」
E資格
- ディープラーニングの実装スキルを証明
- 「受験資格を得るための講座受講が必要だが、体系的に学べて良かった」
資格取得の落とし穴と対策
落とし穴1:資格コレクターになってしまう
「資格をたくさん取れば転職できる」と思い込み、実務経験を積まずに資格ばかり取得してしまうケースがあります。
対策:資格は「手段」であって「目的」ではないことを忘れずに。資格取得と並行して、必ずKaggleやGitHubで実践的なプロジェクトに取り組みましょう。
落とし穴2:難しすぎる資格から始めてしまう
最初から統計検定1級やE資格などの高難度資格に挑戦し、挫折してしまうケースです。
対策:必ず自分のレベルに合った資格から始めること。小さな成功体験を積み重ねることが、長期的な学習継続につながります。
落とし穴3:資格の勉強だけで実践しない
資格の勉強に時間を取られすぎて、実際のデータ分析経験を積む時間がなくなってしまうケースです。
対策:勉強時間の配分を「資格勉強:実践」=「7:3」程度にすること。学んだ知識をすぐに実践で試すことで、理解が深まります。
まとめ
この記事では、データサイエンティストとして活躍したい人におすすめの資格を初学者向けからレベル別・目的別に紹介しました。
データサイエンスに関わる資格は複数存在します。資格を取得することで、体系的に知識を身につけられるだけでなく、就職・転職活動においても大きなアドバンテージとなります。
データサイエンス関連の資格は、初級者向けのもの、中級者向けのもの、またどのような人を対象とするかでさまざまです。自分の現在のレベルや目的に合う資格を取得していきましょう。
資格を取得するだけではなく、ビジネスの現場で役立つ実践的なスキルを確実に身に付けたいという方は、データサイエンティスト育成講座の受講を検討してみてはいかがでしょうか。
私自身も、資格取得と実務経験を組み合わせることで、データサイエンティストとしてのキャリアを築くことができました。資格は「目的」ではなく「手段」であることを忘れずに、自分の目標に向かって一歩ずつ進んでいきましょう。
筆者からのメッセージ
データサイエンティストを目指す皆さんへ。
資格取得は決して簡単な道のりではありません。特に、働きながら勉強を続けることは、時に辛く感じることもあるでしょう。
でも、覚えておいてください。資格の勉強を通じて得られるのは、単なる「合格証」だけではありません。体系的な知識、論理的思考力、そして何より「やり遂げた」という自信です。
私も最初は「データサイエンティストになんてなれるのかな…」と不安でいっぱいでした。でも、一つずつ資格を取得し、知識を積み重ねることで、少しずつ自信がついてきました。
皆さんも、きっと大丈夫です。焦らず、着実に、一歩ずつ前に進んでいってください。応援しています!
次に読むべき記事
データサイエンティスト向け資格について理解を深めたあなたは、以下の記事も参考にしてください:
- データサイエンティストになるには: 資格取得を含む総合的なキャリア戦略
- データサイエンティスト スキル: 資格以外に必要なスキルの詳細
- データサイエンティスト 年収: 資格と年収の関係をより詳しく分析